先見の書『心理学的経営』から学ぶ感情とカオスのマネジメント
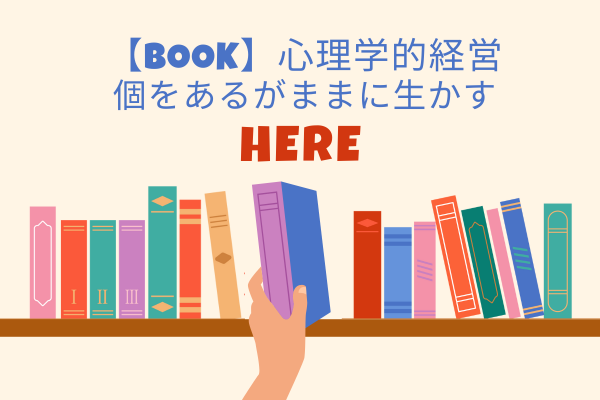
現代のビジネスシーンでは、人的資本経営やティール組織、心理的安全性といった言葉が頻繁に聞かれます。しかし、これらの概念の核心を突く議論が、実は30年以上も前に日本でなされていたのです。それが本日ご紹介する『心理学的経営―個をあるがままに生かす』です。著者はリクルートで人事・組織開発を担った大沢武志氏。
本書は、VUCA時代の現代においてこそ、その輝きを増す「先見の書」と言えるのではないかと思います。特に示唆に富むのが、「感情」と「カオス」という、一見マネジメントの対極にある要素をいかに組織の力に変えるかという視点です。
「裏のマネジメント」― 人間の感情をエネルギー源とする
一般的な経営(表のマネジメント)が制度やルール、合理性で組織を動かそうとするのに対し、『心理学的経営』は、人間の感情や無意識、非合理性といった「裏のマネジメント」の重要性を説きます。これらは決して排除すべきノイズではなく、むしろ組織の創造性や信頼関係を育む土壌であると捉えるのです。
例えば、非公式な雑談や社内のサークル活動、飲み会といった一見非効率な活動が、実はアイデアの交換や部門を超えた信頼の醸成に不可欠な役割を果たしている、と本書は指摘します。社員を「経済人」としてだけでなく、感情を持ち、自己実現を求める生身の人間として尊重すること。その思想が、現代のエンゲージメント向上の議論にも直結しているのではないでしょうか。
「カオスのマネジメント」― 予定調和を壊しイノベーションを生む
本書が提唱するもう一つの重要な概念が「カオスのマネジメント」です。秩序正しく整流化された組織は、効率は良いかもしれませんが、革新的なアイデアは生まれにくい。そこで、あえて「意図的なカオス(混沌)」を組織内に持ち込むことの重要性を説いています。
具体的には、職務の境界をあえて曖昧にしたり、部門横断的なプロジェクトを走らせたり、複線的なキャリアパスを用意したりすること。こうした「揺らぎ」や「遊び」のある状態が、予期せぬ化学反応を生み、イノベーションの苗床となると。これは、変化を前提とし、自己組織化を促すティール組織の考え方とも見事にリンクしています。
VUCAの今だからこそ響くメッセージ
『心理学的経営』が今日でも多くの示唆を与えるのは、その根底に「人間をあるがままに受け入れる」という揺るぎない思想があるからだと思います。合理性や効率性だけを追求するのではなく、人間の持つ感情や矛盾、そしてそこから生まれる混沌さえもマネジメントの対象とし、組織のエネルギーに変えていく。
変化が激しく、未来の予測が困難な時代だからこそ、30年の時を超えて語りかけてくる本書のメッセージは、すべてのリーダーにとって必読の価値があると言えるでしょう。


