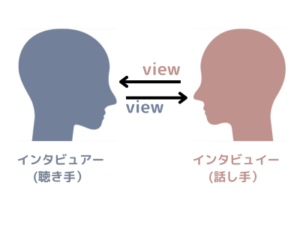心理的安全性が高すぎるチームの落とし穴

「心理的安全性」という言葉が組織づくりのキーワードとして広く浸透してきました。心理的安全性が高い職場では、メンバーが自分の意見を自由に言え、ミスや問題も率直に共有されやすくなります。私自身も、組織開発の現場でその重要性を何度も実感しています。
しかし最近の研究では、「心理的安全性は常に高ければよい」という単純な図式に警鐘が鳴らされています。
2023年の研究(Liat Eldor, Michal Hodor, Peter Cappelli, Organizational Behavior and Human Decision Processes)では、心理的安全性が高すぎることで、かえってパフォーマンスや学習が妨げられるケースがあると示されています。
特に次のような状態では、「心理的安全性の罠」に陥りやすいとされています。
- チームに明確な目標や基準がない
- なれ合い的な雰囲気で、挑戦が避けられる
- リーダーがあえて対立や異論を扱わない
では、どうすればよいのでしょうか。
大切なのは、「心理的安全性」×「健全な対立」×「目標の明確化」のバランスです。心理的安全性は、安心して率直な対話を行うための“土壌”であって、“何を話しても許される空間”ではありません。
リーダーやマネージャーは、あえて異なる視点を歓迎し、議論を促す役割が求められます。心理的安全性の「使い方」を理解することこそが、成果につながる組織をつくる第一歩です。
心理的安全性は目的ではなく、チームの成長と成果のための手段です。「高ければよい」ではなく、「何のために高めるのか」を問い直す視点を、今あらためて持ちたいところです。