部下の「揺れる気持ち」とどう向き合う?――アンビバレンスを力に変えるマネジメントのヒント
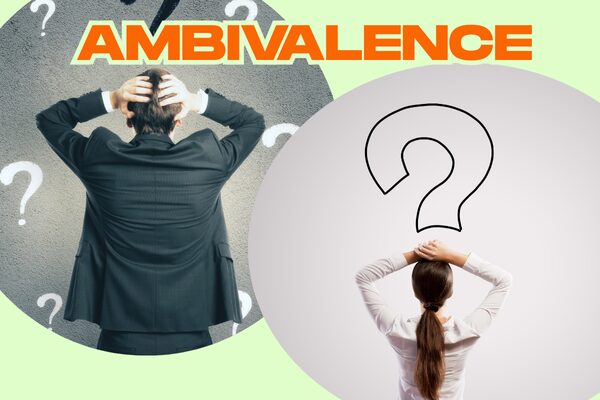
前回の記事では、「やる気」を引き出すには“正しさ”を押し付けるのではなく、部下自身の中にある「変わりたい理由」を引き出す対話が大切だとお伝えしました。
でも実際には、部下の心の中には「変わりたい自分」と「今のままでいたい自分」が同居していることが多いものです。この“アンビバレンス(両面性)”は、決して悪いものではありません。むしろ、誰もが持つ自然な心の動きです。
アンビバレンスを否定しない
「やる気がない」「迷っている」と感じる部下を前に、つい「どっちなの?」「はっきりしなさい」と迫りたくなることもあるでしょう。でも、アンビバレントな気持ちを否定したり急かしたりすると、かえって部下は心を閉ざしてしまいがちです。
「やる気が出ない自分も、変わりたい自分も、どちらも本当の気持ち」
まずはそう認めることから始めましょう。
アンビバレンスを力に変える3つのコツ
1. 迷いを言葉にしてもらう(両面を可視化する)
「やりたい気持ち」と「やりたくない気持ち」それぞれについて、あえて両方を聞いてみましょう。
- 「やってみたいと思う理由はどんなこと?」
- 「逆に、踏み出せない理由や不安は何?」
部下が自分の中の矛盾を言葉にできると、気持ちが整理されやすくなります。
2. 判断を急がせず、“揺れ”を一緒に味わう
「どちらの気持ちも持っていていいんだよ」と伝え、すぐに結論を出させるのではなく、しばらくその“揺れ”を一緒に受け止めてみてください。
- 「迷うのは自然なことだよ」
- 「どちらの気持ちも大事にしていいと思う」
この“保留”の時間が、部下の自己理解や納得感を深める土台になります。
3. 小さな一歩を一緒に考える
「100%やる/やらない」ではなく、「まずはここだけやってみようか?」という小さな行動目標を一緒に探してみましょう。
- 「全部やるのは難しくても、まずはこの部分だけ試してみるのはどう?」
- 「不安な点があれば、サポートできることはあるかな?」
小さな成功体験が、次の行動への自信につながります。
「揺れ」を尊重することで生まれる主体性
アンビバレントな気持ちは、決して「優柔不断」や「やる気がない」証拠ではありません。むしろ、部下が本気で自分と向き合っている証拠です。
リーダーがその“揺れ”を否定せず、寄り添いながら一緒に考えることで、部下は「自分で選んだ」という納得感を持って行動できるようになります。
「迷いながらも進む」――そのプロセスこそが、部下の成長の原動力になるのです。
まずは、面談や1on1で「どちらの気持ちもOK」と伝える一言から始めてみませんか?
部下の“揺れる気持ち”を尊重することが、チーム全体のしなやかな成長につながっていくはずです。
【注意】このアプローチの目的と限界
このブログシリーズは、あくまで業務上のコミュニケーションを改善し、パフォーマンスを向上させるためのヒントとして認知行動療法を取り上げています。管理職はセラピストではありません。部下の精神的な問題には深入りせず、必要に応じて産業医や専門家につなぐ役割に徹してください。扱うテーマは仕事上の課題に限定し、部下のプライベートな問題には踏み込まないことが重要です。下記のガイドも併せてご参照ください。


